コーヒーを上手く淹れたいけどコツが分からない。そもそも「コツ」って何?コーヒー通が語る薀蓄って、どこまで信用していいの?そんな疑問に答える本を見つけました。これからコーヒーの道に進みたい人も、ワンランク上のコーヒーを目指したい人も、コーヒーを注文する時やコーヒー豆を買う時に小洒落たことを言ってみたい人も参考にできる本です。
私がこの本を最初に見つけたのは、あるカフェの本棚でした。コーヒーが好き過ぎてカフェめぐりをしている私は自宅でももちろんコーヒーを淹れるのですが、当時の私は(今もそうなんですが…)思ったように上手くコーヒーを淹れることが出来ず悩んでいました。行く先々のカフェでバリスタさんにいろいろ教わりつつも、何かコーヒーについて体系的に学んでもみたい。そんな時に見つけたこの「コーヒー『こつ』の科学 – コーヒーを正しく知るために」はいろんな疑問に答えてくれました。
コーヒーを正しく知るために
はじめに申しておきますと、こつの「科学」と言っても、理系の人向けに書かれた本ではありません。理系科目に苦手な人も無理なく読める内容です。また私のように趣味でコーヒーを淹れている人はもちろん、仕事でコーヒーを扱うプロに向けた内容にもなっています。
「コーヒー『こつ』の科学」の概要
1. コーヒーを知るための基礎知識
コーヒー豆について、それがコーヒーノキという植物の種子であることから、嗜好飲料としての歴史や一杯のコーヒーになるまでの過程まで、そこそこ詳しく述べられています。
美味しいコーヒーを淹れるためにその知識は必要か、と問われると正直困りますが、一杯のコーヒーを楽しむその背後に秘められたストーリーとして興味深いものがあります。コーヒー談義が好きな人には話のネタにもなるでしょう。
2. コーヒーの成分を知る
コーヒーに含まれる成分について、カフェインはもちろん、苦味や酸味から甘みや香りまでコーヒーの味を左右する様々な成分の特徴から変化まで、かなり詳しく説明しています。
一見したところコーヒーにまつわるマニアックな科学知識に思われますが、読み進めていくと美味しいコーヒーを上手く淹れるために必要な基礎知識であることが分かります。
3. おいしいコーヒーを淹れるために – 買い方、抽出方法、挽き方、保存方法
コーヒー豆を選ぶ基準、買ったコーヒー豆から一杯のコーヒーを淹れるために必要な様々な器具の特徴や抽出方法から注意事項、また淹れ方による味の違いの科学的説明まで詳細に述べられています。全5章の中で一番多くページ数を割いています。
私のように「自分で美味しいコーヒーを淹れたいんだ!」という人が一番気にするところでしょう。コーヒーを上手く淹れる方法を説明する本は多々ありますが、科学的知見を基にここまで説明するのは流石です。コーヒー豆を挽いた粉から苦味成分と酸味成分が抽出されるまでの時間差などの説明は目からうろこでした。
4. コーヒーの加工を知る – 生豆の扱い方、焙煎、ブレンド、包装
まずコーヒー豆について、生豆とその焙煎方法を詳しく説明しています。ブレンドについては、そもそもなぜブレンドするかの説明に始まり、プロが行うブレンドの方法が詳説されます。最後は焙煎したコーヒー豆の包装についてです。
この章は主にプロ向けに書かれていることが分かります。例えば焙煎について、焙煎の科学的説明の他にも多くの部分を業務用の焙煎機の仕組みやその使用方法の詳説に割いていて、最後に家庭でできる焙煎について説明しています。包装については明らかにコーヒー豆を販売する人が必要な情報でしょう。
5. もっとコーヒーを知りたい人のために – 栽培、精選、流通、品種
コーヒー豆が流通するまで、その栽培方法から精選方法、また輸出入の過程までいろいろ述べられています。
私のような素人にとっては雑学的な内容にはなりますが、コーヒー豆の買い付けを行う人にとっては大事な情報でしょう。私が個人的に好きなのはオーガニックコーヒーについての説明です。オーガニックであればありがたい、ということではなく、味の良し悪しは作り方次第、それも最終的には飲む人の舌が判断する、ということです。
この本のここが好き
この本の「はじめに」でも述べられているようにプロからアマまで読める幅広い内容の本ですので、読んだ人の感想も様々でしょう。以下はコーヒーが好き過ぎて趣味でコーヒーを淹れている私の感想です。
個人の好み、スタイルが大事
タイトルに「科学」とあると画一的な説明をすると思われるかもしれませんが、例えば上述のオーガニックコーヒーの記述のように、美味しいかどうかを決めるのは個人の好みであることが述べられています。他にも、コーヒー豆を焙煎することで生まれる風味を科学的に説明した後、その後時間とともに起こる変化について述べていますが、この変化は人によって「劣化」となり、同じ変化が人によっては「熟成」になるとも述べています。
科学的にこれが良い、と言うのではなく、好みの違いが分かれることを科学的に説明する、そんなところが好きです。
プロ向けの内容はアマチュアへの勇気
全体的にプロもアマも読める内容が多く、上述のように4章は特にプロ向けの内容が濃いように思われます。しかし、そのような内容はアマチュアには関係ない、ということではなく、そんな本が一般人の手に届くところにあるということは、アマチュアでもプロのような味を出すことができる、という勇気を与えてくれていると私は思います。
最近私は手網を使ったホームローストにはまっています。自宅焙煎コーヒーの味は格別ですが、いくらコーヒーが好きだと言っても、自宅に大型の焙煎機を置く人はまずいないでしょう。それだけを考えると4章で説明している焙煎機の扱い方は一般の人には関係ないように思われますが、その内容には私のようなアマチュアが学べることもありますし、自分も自宅でこんな味を出したい、という動機付けにもなります。
コーヒーを正しく知るために
最後に
このカフェめぐりブログの他にも私は英語学習の四方山話を綴った「可能性の扉」というブログも書いていて、そこで度々「習って慣れろ」という話をします。私は今まで「英語は習うより慣れろだ」と豪語する人に何人も会ってきましたが、そんな人の中でまともな英語を話せる人は少ないのが現実です。笑顔で分かり合える外国人の友達を作ることが目的であればそれでもいいかもしれませんが、ビジネス英語ではそうはいきません。受験英語で誤った知識を刷り込まれてきた私達には正しい「活きた」英語を習い、それに慣れる必要があると私は考えています。コーヒーも同じではないでしょうか。
私自身、コーヒーをなんとなく勘に頼って淹れて、コーヒーの味は淹れるたびに味が変わるから難しくて面白いのさ、なんて言っていた時期が長くありました。それはそれで楽しいものではありますが、理屈を理解してちゃんと淹れれば素人でもそこそこ安定した味を出すことができるようになります。もちろんそこには「慣れ」も必要ですが、「習う」部分の助けになるのがこの「コーヒー『こつ』の科学 – コーヒーを正しく知るために」でしょう。


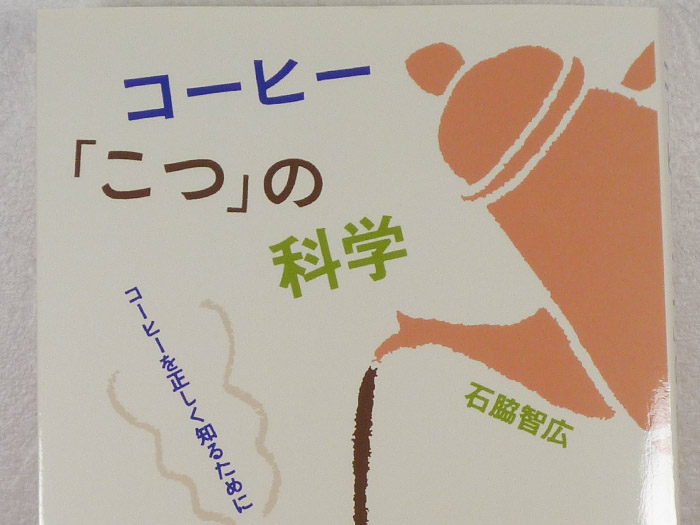






コメントを残す